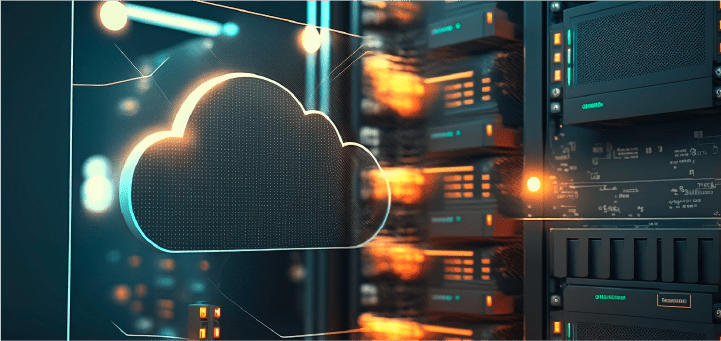クラウドバックアップサービス AvePoint

クラウドバックアップは、企業が管理するデータの安全性を高める重要な対策です。
本記事では、クラウドバックアップの概要やオンプレバックアップとの違い、重要性、種類、メリット・デメリット、導入のポイントなどについて解説します。
※本記事に掲載している情報は2024年3月時点のものです
目次
クラウドバックアップサービス AvePoint
「クラウドバックアップサービスAvePoint」導入でグループウェアの
情報セキュリティリスクを軽減。「グループウェア」のデータ保護を実現します。

クラウドバックアップとは、企業が管理するデータをクラウド基盤上の仮想サーバーに複製・保管する方法です。
以下に示す2つの方法のうち、どちらかを利用してバックアップを取ります。
クラウドバックアップを取っておけば、社内で管理しているデータが消えても、複製したバックアップデータを使ってサービスやシステムを復旧できます。
また、仮想サーバーは企業外部に設置するため、企業内で問題が起きても仮想サーバー自体に影響が及びません。頻発する地震や水害からデータを守ることはもちろん、第三者からの攻撃からデータを守るランサムウェア対策として活用できます。
クラウド上にバックアップデータを管理する「クラウドバックアップ」とは別に、オンプレバックアップという方法があります。
オンプレバックアップとは、社内またはデータセンターをLANケーブルや専用線でつなぎ、バックアップデータを複製・管理する方法です。
参考として、クラウドバックアップとオンプレバックアップの違いを表にまとめました。
| 費用 | 導入しやすさ | 拡張性 | 転送速度 | 保守・メンテナンス | |
|---|---|---|---|---|---|
| クラウドバックアップ | 設備を準備せずに済むため安価 | 早期導入が可能 | 素早く機能を追加できる | ネット管理なので処理に時間がかかる | ベンダーが負担 |
| オンプレバックアップ | 設備投資が必要なため高価 | 構築に時間がかかる | 構築に時間と費用がかかる | 素早くバックアップを取れる | 自社負担 |
クラウドバックアップは、コストが低く、素早く導入できるのが特徴です。また、企業が定める要件変更やデータ容量の増加にも素早く対応できます。
注意点として、オンプレバックアップと比べて転送速度に劣ることがありますが、データの転送速度はサービスの比較検討によって解決できます。早急な災害対策やランサムウェア対策を検討しているのなら、クラウドバックアップに優れる点が多いと覚えておきましょう。

近年、インターネットサービス・システムの普及により、クラウドバックアップの重要性が高まっています。
なぜクラウドバックアップが必要なのか、サービス・システム運用で起こりうる3つのリスクを紹介します。
インターネットサービス・システムの運用には、データ消失のリスクが伴います。
例えば、災害やサーバーが故障した際にデータが消失してしまう恐れがあります。クラウドバックアップを利用すれば、自動でバックアップされるほか、問題が起きた際に通知が届くため、もしものデータ消失トラブルにおける早急な問題解決が可能です。
インターネットサービス・システムを運用する際には、ウイルス感染のリスクに注意しなければなりません。
例えば、社内従業員の操作でウイルスに感染した場合や、第三者から悪意のある攻撃を受けた場合には、データを素早く復旧する必要があります。また、データを不正に暗号化して企業に身代金を要求してくるランサムウェアのトラブルが起きるかもしれません。大規模な被害につながるケースもあるため、データを複製して保管することが重要です。
インターネットサービス・システムの運用で問題化しやすいのが、情報漏えいのリスクです。
サービス・システム利用者の個人情報が外部に漏れてしまう場合があるほか、流出したデータを第三者が悪用するかもしれません。リモートワークの普及によって情報漏えいの発生率が高まりつつあるため、安全にデータ管理できるバックアップ体制を整備することが重要です。

クラウドバックアップには、以下に示す3種類の運用方法があります。
バックアップ体制の違いを詳しく説明します。
イメージバックアップ対応型とは、以下に示すデータをまるごとバックアップする体制のことです。
ほぼすべてのデータをクラウド上に複製するため、データ復元が必要なトラブルが起きても比較的短時間で復元できるのが特徴です。
しかし、バックアップするデータ量が多いため、バックアップ処理に時間がかかることに注意しなければなりません。
AI技術の革新と同時に、カメラそのものの性能も格段に向上しています。人間の目と同じレベルの高い解像度で映像や画像を捉えられるようになり、結果的にAIの判断をより正確なものにしています。
また、眼球並みの小ささでも高い解像度の映像が撮影できるようになり、高度な画像認識を活用できる場が広がっているのも大きな変化です。
ファイルバックアップ対応型とは、ファイル単位でデータを複製する方式のことです。必要なファイルだけバックアップを取るため、処理が早くクラウドストレージの容量を節約できます。
ただし、アプリケーションやOSといった基盤データを複製できないため、トラブルが起きた際に、再インストールや設定の手間がかかります。また、アプリケーションを自社開発した場合には、復旧に大幅な時間がかかるケースもあります。
ファイルストレージ併用型とは、クラウドバックアップサービスと一緒に、既存のクラウドストレージサービスを併用する体制のことです。例えば、次のようなクラウドストレージサービスを利用します。
無料版のクラウドストレージサービスを活用できるため、コストを抑えやすいのが魅力です。
ただし、複製したいデータ容量が大きい場合には、有料版に切り替えなければなりません。クラウドストレージサービスの中には、自動バックアップ機能が搭載されているサービスもあります。

クラウドバックアップを取るメリットを3つに整理しました。
導入がおすすめな理由を詳しく説明します。
クラウドバックアップは、ほかのバックアップの手法と比べて初期・運用費用を抑えやすいのがメリットです。
参考として、クラウドバックアップとオンプレバックアップの費用の違いを整理しました。
クラウドバックアップにかかる費用はいたってシンプルです。
ベンダーが提供しているサーバーを使って手軽にデータを複製できるほか、安価な月額費用で運用できます。
クラウドバックアップは、データ容量に合わせて自由にカスタマイズできます。
例えば、契約しているデータストレージの容量が上限を超えてしまいそうな場合には、その場ですぐに容量を変更できます。データ移行といった手間もかからないため、拡張性に優れたデータ複製方法だといえるでしょう。
一方、オンプレバックアップでは、サーバーの増設やデータ圧縮業務を自社で実施しなければなりません。人件費がかかることはもちろん、サーバー追加費用がかかります。
クラウドバックアップの活用は、災害対策として効果を発揮します。
自社オフィスでデータを管理した場合、災害によるデータの破損・消滅の恐れがあります。一方、クラウドバックアップを使って遠方にあるサーバーを活用すれば、企業が災害対策として実施しなければならない「DR」「BCP」を強化できるのが魅力です。
対してオンプレバックアップの場合には、自社オフィスもしくは近隣のデータセンターにバックアップを取ることが多いため災害対策に劣ります。もしもの備えを検討している場合、リスクを分散できるクラウドバックアップがおすすめです。
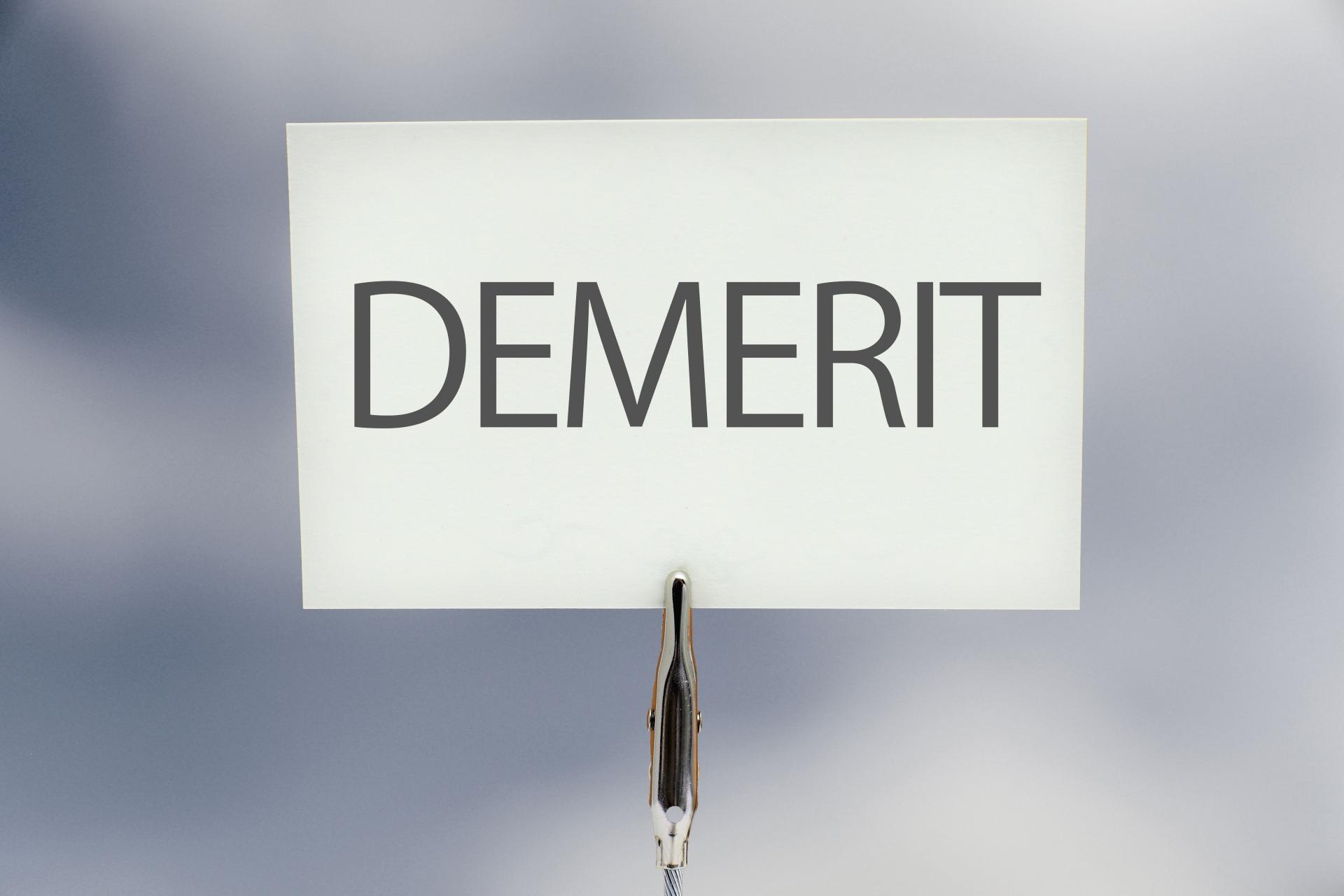
クラウドバックアップには、デメリットもあります。
活用が難しいケースについて詳しく説明します。
クラウドバックアップはインターネット環境を利用してバックアップを取るため、インターネットに接続していなければデータを複製・管理できません。
インターネット接続環境が不安定な地域にある会社だと、クラウドバックアップの利用が難しいと覚えておきましょう。
クラウドバックアップはインターネット接続下でデータを複製・管理するため、通信速度が安定しにくいです。
大量のデータを複製する際に時間がかかることはもちろん、復旧にも時間がかかります。特に容量の大きいデータの場合には、通信速度が遅くなるケースがあると覚えておきましょう。
ただし通信速度の問題は、クラウドバックアップサービスの選択によって解決します。検討時は通信速度といったスペックを比較しつつ、高速でデータ処理できるサービスを選ぶとよいでしょう。
自社独自のセキュリティ要件がある場合、クラウドバックアップを導入しにくい場合があります。なぜならば、クラウドバックアップは、ベンダーが提供している仮想サーバーの要件に準じて利用しなければならないからです。
クラウドストレージの容量変更といったカスタマイズは簡単に実施できますが、バックアップ体制の詳細設定は実施できません。もし自社独自のセキュリティ要件を満たす必要がある場合には、クラウドバックアップサービスの比較検討やオンプレバックアップとの併用を検討してみてください。

クラウドバックアップサービスの導入を検討している方向けに、3つの選び方を紹介します。
自社に最適なサービスを見つける参考にしてみてください。
クラウドバックアップサービスは、安全を考慮してセキュリティ性が高いものを選びましょう。
なぜなら、企業が運用しているサービス・システムには、次のリスクがあるからです。
上記のリスクは、どれも人力による管理で起こりやすいリスクです。
また、第三者から攻撃を受けて問題が起きるケースが多々あります。
インターネットサービス・システムの場合には、膨大なデータを管理する企業も少なくないため、データの暗号化やログ保存、自動バックアップといった機能が搭載されたクラウドバックアップサービスを選択しましょう。
クラウドバックアップサービスは長期的な運用が前提です。継続して費用を支払えるサービスを選びましょう。
企業によっては機能性を重視しすぎた結果、途中で支払いが困難になるケースも多々あります。クラウドバックアップサービスは初期費用・運用費用というシンプルな構成で金額を計算できるため、1年、5年、10年というように、長期利用した場合の金額を比較しながらサービスを選択してください。
災害対策のひとつである「BCP対策(事業継続計画)」としてクラウドバックアップサービスを導入するのなら、次のポイントを比較しながらサービスを選びましょう。
例えば、利用するクラウドバックアップの拠点によって、災害の起こりやすさが違います。
また、設備の新しさ、追加やカスタマイズの余裕の有無も異なるため、比較検討が欠かせません。BCP対策は、すべての企業に必要とされる取り組みですので、自社の要件に合うクラウドバックアップサービスを選択してください。
BCP対策について詳しく知りたい方は、以下の記事がおすすめです。BCP対策が義務化された背景やメリット・デメリットを説明しています。
関連記事:「BCP対策とは?義務化された背景や国内事例を簡単に解説」

クラウドバックアップは、企業データを安全に管理する重要な対策です。
また、オフラインでの管理や外部からの攻撃による「データ消失」「ウイルス感染」「情報漏えい」といったリスクを回避するために重要な取り組みだといえます。
もしバックアップデータの管理にお悩みなら、クラウドバックアップサービスの導入をおすすめします。
オフラインで管理しているデータを、まるごとクラウドの仮想サーバーに移行できるのはもちろん、オンプレバックアップからクラウドバックアップへの移行も可能です。導入ハードルが低いほか、すべての企業に必要なBCP対策としても有効ですので、業務に活用していただけると幸いです。
※本記事における価格情報記載はすべて税抜表記です。
※Microsoft、Windows、Windows 10およびMicrosoftのロゴは、米国およびその他の国におけるMicrosoft Corporationの登録商標または商標です。
※その他、記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。
「クラウドバックアップサービスAvePoint」導入でグループウェアの
情報セキュリティリスクを軽減。「グループウェア」のデータ保護を実現します。